皆さん日々研修・学習していますか?
学童保育の支援員としての能力を向上させるために皆さんも日々勉強している事でしょう。「外部の研修に積極的に行って学んだり、クラブ内の研修をして日々、自分での学習」保育の為に自己研鑽している事と思います。
このブログを読んでくださっている皆様もおそらく「何かしらの学びにならないか?」、「保育のヒントになることはないか」、「保育の悩みを解決する方法はないか?」という気持ちもどこかにありつつ来ている方もいらっしゃると思います。
そんなあなたにとても良い方法を今回の記事から書いていこうと思いますので、興味があれば是非とも最後までお読みになってもらえればと思っております。何回かに分けて書くことになると思いますのでよろしくお願いします。
前置きになってしまいますがその前に学ぶということを考えていきたいと思います。
学ぶという事は
- 講義や書籍等から知識の量を増やす
-
一般的な学びの方法ですね。学校教育やセミナーなどでも行われている、教科書やテキストを使って講義があり、知らなかった事を知り、さらにより深いところまで知ったり考えたりすることです。
- 実際に体感し覚える
-
こちらも一般的な学びの方法です。こちらは座学ではなく実技系の学びとなります。
他者に自分の知識や考え方を伝える・教える事も学びとしては有効です。分かりやすく説明をするために自分の中でも整理する事にもなるからです。勉強だけに限らず様々な分野で教えあいの手法が学びの場面で取り入れられていることもあります。
最近ですと動画をYoutubeにアップしたり、このようなブログなどを公開している方も多く、公開する為にはある程度以上の学びが必要になります。
自分より知識や経験がある方から、まとめられている書籍や動画などから学んでいく事が基本であり、他者に教えることによる学びもあります。多くの方がこの3つの方法で学んでいる事でしょう。
保育における有効な学びとは・・・
教科書に記載されているような知識を増やしたり、体験してできるようにしたりすることももちろん重要ですが、保育における有効な学びの方法があります。それは・・・
自己の保育実践から学ぶという事です
保育の知識を学んだり、子どもへの関わり方・声掛けなどを学ぶ事も大事ですが、そういった教科書に書かれている事よりもはるかに効果が期待できると私は思っています。そんなに効果があるの?してこなかった方々は正直やらなければ損してしまいますよというレベルの事になります。
ではどのようにして「自己の保育実践から学ぶ」事ができるのでしょうか?
保育実践を書いてみましょう
自分のした保育実践を「言語化」し書いてみることがまずは第1歩となります。この自分の保育でしてきたことを「言語化」するという事がまずは必要となってきます。他者の実践を見学などから書いてみる事では効果が起こりませんのでご注意ください。「言語化」関する事については次に紹介する記事に記載されていますのでまずはそちらを必ず読んでいただければと思います。
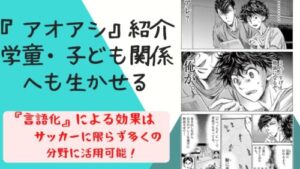
先に「言語化」について書いた『アオアシ』の記事は読んでいただいたでしょうか?一応こちらにも抜粋しておきます。言語化をすると良い事は私が考える3つがあります。
- 成功、失敗どちらも振り返る事ができる。
- 「理解度」や「経験知」が高まり再現性が高まる。
- 言語化して知識や経験として蓄えられたものを応用・組み合わせて活用できる。
[ad01]
自分の実践を成功失敗、良かった事悪かったことを振り替えることができます。その時に「何を思っていたのか?何を考えたのか?なぜそのようにしたのか?」きっと今挙げたこと以外にも多くの事を思い返すでしょう。
その振り返りこそが必要となるため「言語化」が必要となるのです。そして、自分の実践でないとその時に「何を思っていたのか?何を考えたのか?なぜそのようにしたのか?」が想像でしか分かりませんよね?だから自分の実践でないとならないのです。
「再現性」というのは同じような結果が起こるとでも言い換えると分かりやすいでしょうか?成功したことはまた成功し、失敗を防ごうとすればうまく防げる状態となります。「言語化」しその物事の理解や経験が深まる事で自分のしたい事ができる可能性が高まるという事になります。
「なぜうまくいったのか分からない・・・」「たまたまうまくいった」「運よく何も起こらなかった」というような分析だとせっかくうまくいったことも次は起こらない可能性が高まり、うまくいかなかったことを防ぐこともできないでしょう。
「言語化」できていない事は応用も組み合わせも高確率でできませんし、他の事柄へ繋がっていきません。さらなる力量の向上には応用や組み合わせも必要になってきます。
このコマをご覧ください。葦人が自分のプレーの考えを冨樫に伝わるように言葉に落とし込む事をしています。

そうすると「これ・・・すげえ勉強になるぞ」
『俺が』
葦人の視野の広さについて冨樫から教えて欲しいと言われた場面になります。自分では自然とやっている事でも、人に説明するためにでも「言語化」するととても勉強になるのです。
[ad01]
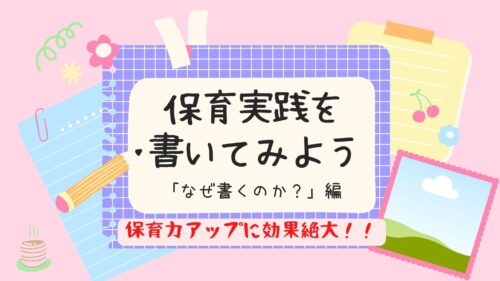
コメント