連携はとても大切ですよね
連携についての記事は以前にも書いていますので、今回の記事を読んでいただく前に見ていただきたいです。読まなくとも職員間の連携は大切だよ!なんてみんな分かっているかとは思いますが、是非とも読んでいただきたいです。
なぜ連携を高めることは難しいのか?うまくいかないのか?
原因はそれぞれにあると思います。あげたら色々と出てくるでしょう。
連携がうまくいかないという事になると、同じ仕事をするにしてもストレスが大きくなってしまい、人間関係の悪化にもつながっていきます。
そうなってくると仕事の内容は大丈夫なのだが、人間関係で辞める・離職につながってしまいます。
課題についても先の紹介記事にも書いておきましたが、ここではより深く考えていきたいと思います。
勤務時間のずれや職員不足による課題
勤務時間の関係や職員の人数不足は課題としては、多く上がる事ではあります。時間がずれて連携をとるための打合せができない等、職員不足などの時間的・人員的な課題でしたら原因がはっきりしているので解消はしやすいと思います。
しかしながら、工夫やお金を使っての広告掲載などが必要となるため即時解消という訳にはいかない事も多々ありますので、運営担当者・主任・リーダー・施設長どのような立場の方が決めるのかはそれでしょうが、少し先を見越して動いていき不測の事態にも対処できるようにしておきたいところです。
時間のずれは直接会わなくともやり取りができる工夫などで解決はできそうです。直接話せないようなノートやメールを使うなどは真意が伝わりづらい事もあるので注意が必要です。
職員不足は人員の増加でしか対応できないかもしれませんので、人材採用担当など担当がいれば事情を説明し人を集めてもらいましょう。現状、学童保育業界は人手不足感も否めないので解消には時間がかかるかもしれませんが、動かない事に工夫仕様が改善しない事も多いので動いてもらいましょう。
人材不足をそのまま放置しておくと1人当たりの業務的負担が高まり、「連携が取れない以外の問題点や不満」が出てくることが高確率で起こりますので早急に解決に向かい動いて下さい。
私が思う大きな原因は次のところです
次の「アオアシ」のコマみて下さい。この前後のページも紹介したいのですが、(あれば掲載しておきます)
葦人・冨樫のチームが失点後に言い争いを始めてしまっています。以下のようなやり取りで言い争いと言うより冨樫が一方的に言っています。
冨樫「葦人ォ!」「テメエ、寄せが甘いんだよ!」「行くなら行く、行かねえなら行かねえ・・・」「ハッキリしろや!」
アオアシ14 第139話より
葦人「ええーーーー!」「お、俺、寄せ甘いのか!?」
冨樫「当たり前だフラフラしやがって」「もっと中ケアしながらポジション取れってんだよ!!」
日常生活でも良くありますよね。いわゆる「察してくれよ」というやつです。おそらく多くの人が1度は思ったことがあったり、考えたことがあったりしたことでしょう。私も思った事、考えた事もありますし、言われたこともあります。私自身はこの手の事を言われると最近は非常に不快です。
日本では多くの場所であることでしょう。少し前には「忖度」という言葉で大きな事もありましたよね。日本では「察してくれない人」の方が鈍感、不親切、気配りが足りないとされ、また、察することは相手を大切にしていることの表れとされています。しかし、必ずしも「察してくれない人」は悪く言われ、察することは相手を大切にしていることであると言えるのでしょうか?
よくよく考えてみると冨樫のように「自分の事を察する事」を相手に求める事は自己中心的な事でもあると思います。福田監督(右下コマ)の言うように「なぜ事前に指示をしない」となってしまったのでしょうか?事前に指示や確認をしておけば、必ず失点を防げた訳ではありませんが、次につなげていく事が可能です。
福田「余計なプライドが邪魔してるんなら今すぐ何とかしろ」「お前が一番Bに近いぞ。」
アオアシ14 第139話より
冨樫「・・・・・・!!」
事前に言わなかった本当の理由はあらすじ内では描かれていないので、推測でしかできませんが、冨樫的には痛いところを突かれた感じで考え込むようになっていました。福田監督が言うように「お前のプレーには対話が無い」という事になります。
[ad01]
連携の高まらない原因の大きな部分はコミュニケーションに問題がある
アオアシの内容より長くなってしまいましたが、私の思う連携が高まらない大きな原因は「コミュニケーション不足」であると思います。まずは今回紹介した「分かってくれるだろう、思っている事を汲んで動いてくれるだろう」という事を変えていく事が必要だと私は考えます。
ひどい人だと何かが起こった後に「私はそうなると思ってたのよねぇ、それとなく言っておいたんだけどねぇ・・・」みたいな酷いことを言われることも多くあるかと思います。
日本的なコミュニケーションの手法ではありますが、正直組織での連携にはあまり向いていません。
施設長・主任・リーダー的な人が「分かってくれるだろう、思っている事を汲んで動いてくれるだろう」というような方法をとっていたら、おそらく他の職員は言わないにしても良く思ってはいません。
職員の中でもこのような考え方をしている場合、自分の考えが分かってもらえない伝わらないなど間違った認識となり苦しむことになるかもしれません。
大人もコミュニケーション能力が低いということ、またはできていると勘違いしている状態になってしまいますよね。しっかりとした考え方やそれまでの前段階があり自分で気づいて欲しい等の明確な意図があれば敢えて言わないも良いとは思います。
「察してよ!」と言ってくる人の多くは考えや明確な意図もなく習慣的・無意識的にやっていると思います。お互いの考えや思い、伝えなけれならない事、その他『伝え合うこと』が必要になるのです。
みなさんの所属クラブではこの「伝え合うこと」がきっちりとできているでしょうか?今、できていると思った人はもう1度思い返してみると良いと思います。
多くの人が伝わっている・できていると思っているからこそ全然改善がされていかないのでしょう。
[ad01]

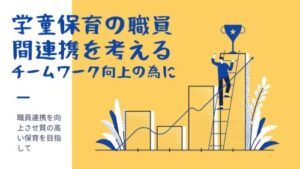
コメント