辞めたくなったら読んでみて下さい
このページにたどり着いたあなた。学童勤務の方はもしかしたら勤務のたびに「仕事に行きたくない」「仕事を休みたい」「今日こそ辞める」などと思っているでしょう。
以前に【学童保育で働くことに悩んだら読むページ ‐指導員向け‐】を書きました。
今回は更にその先『辞めたくなった時』についてを書いていこうと思います。
おそらくはご自身でも勉強したり、相談したり、何とか続けられるようにしている事でしょう。それでもどうにもならなそうな場合はその先も考えていかなければなりません。
どうしても今現状、『学童を辞めたい場合』は読んでみて下さい。何か1つでも参考になることがあるかもしれません。本来はこんなことは無い方が良いとは思っていますが、起きうることなので書いておきます。
辞めたい理由を整理する
 KJ
KJまずは自分が”なぜ学童指導員を辞めたいと思ったのか?”、具体的に理由を整理しておくことが大切です。



色々とありそうだけど、「人間関係が悪くてストレスがたまっている」、「仕事内容にやりがいを感じられなくなってしまった」、「自分のスキルや興味に合わなくなってしまった」、「収入が少なくて生活ができない」等が考えられそうね。
その理由や原因がうまく解決する、そもそも無くなってしまうというようなことが偶然にも起こればそのまま続けることができるかもしれませんしね。
例えば、人間関係で上手くいっていない場合、相性の悪かった人が急遽退職や異動になったなんてことが起こらないとも言い切れませんのでラッキーがあって解決なんてこともあります。
他力本願やラッキーを願っていてもなかなか降っては来ないので、しっかりと自己分析をして、今思っている事、辞めたい理由、その他を整理することが第1歩となります。
その事業所が悪い・良くない・合わなかっただけ
うまくいかない時のメンタル的には『自分を責めがち』『相手のせいにしがち』のどちらかになる傾向があると思います。
あなた自身が悪い・あなた自身の能力が足りないという事では無い場合も多々あります。
その勤務先の方針・方法が合わなかった
学童と言えど単純に一括りにはできません。同じ地域にあってもその保育方針は場所によっては違っている場合もたくさんあります。
とても自由な方針の学童もあれば、習い事のプログラムばかりの学童もあるでしょう。
面接時や入職前時に確認や説明は受けているとは思いますが、細かなところでの「ニュアンスの違い」や「個人の感覚の違い」は出てくるでしょう。感じ方の違いは確実に生まれてくるものです。
対話を重ねて意識の違いを擦り合わせていき、ズレを解消していきますが、うまくいかない場合には余計にズレが大きくなっていってしまうことも有るでしょう。
そうなってしまうとその場所で働き続けることが困難になってきます。
どちらが悪いという訳でもありませんよね。なので余計に解消が難しいと私は思います。
その勤務先の人間関係が合わなかった
保育方針・方法・目標が合わなかったのと同じのようにその時の勤務場所での人間関係次第ではうまくいかなくなるケースもあります。



『児童との人間関係』、『保護者との人間関係』、『職員同士の人間関係』、その1つでもまたは複数においての関係が上手いかない場合、仕事を続ける事に難しさを感じる事も多いと思います。



何かのきっかけや原因があっての拗れでしたら、その要因を取り除けば改善されるんだけどね。
それでも、改善されない場合・明確な原因がはっきりしない場合は続けることが難しいかもしれないわね。
もちろん、皆さんも自分に合わない人もいる事は百も承知で働いている事と思います。それでも割り切れず上手くいかない事なんて仕事以外でも山のようになるでしょう。
どちらの場合も・・・



保育方針にしろ人間関係にしろ、入職した時、異動した時のたまたま感がどうしても強くなってしまい、運の要素も入ってきます。最近よく耳にする『ガチャ的要素』ですね。



面接のときや入職前に確認している場合も多いとは思いますが、基本良い事しか言わないですからね・・・(良くない事を言うと誰も来なくなってしまいますからね)
全ての事が分かった上で働くことなんてありえないですし。
「こんな場所だったら断っていたよ!」などと思っても、もうすでに後の祭りとなってしまっているので、自分自身が納得できないのならば「何とかその場所に残り変えていくか、別の場所に異動、転職するか」になってしまいます。
あなた自身の能力が低く上手くいかない、あなた自身がダメで上手くいかない訳では無い事も実際問題多いと思います。
どうしても自分の実力不足だった
自分の実力不足であった場合、この場合は相手が悪い、場所が悪いと騒いでも誰も取り合ってくれなくなりますよね。
自分の足りなかった部分は真摯に受け止め改善できるようにはしたいところですが、現在在籍の場所ではうまくいかなくなってしまっている現状も多くなってしまっているとは思います。



挽回できれば良いのですが、中々難しい場合は違う学童、違う分野へと転職することになります。
学童業界に残る場合でしたら、自分の実力不足だったことは次に生かせるようにして、何度も同じような状況に陥る事のないようにはしたいです
うまく行っていない現状では気持ち的にも自分が悪かったと思いすぎてしまったり、相手が悪いと決めつけてしまっていたりするメンタルにも陥っている場合も多いでしょう。
このようなメンタル状況では辞めるしても続けるにしてもどちらにしても良くないので、しっかりと休みましょう。そして、冷静に自分を見つめなおすことが出来てから動き出しましょう。
学童業界での労働者へのサポートは不十分



仕事をしていく上で上手くいかない場面に出くわすことも有るでしょう。働くことが困難になった時にも大企業などの体制が整っている組織ならばサポートもしてくれるでしょう。
学童ではどうでしょう・・・。
そんなサポート体制が取れる場所はほとんどないでしょう。良い所でも主任だったりチーフだったり園長だったりが相談に乗ってくれるくらいでしょう。



結局、その主任だったりチーフだったりも同僚の1人に過ぎず、メンタル的なサポートをしてくれる専門家でもないですしね・・
専門家に相談したいならご自身で探すということになるでしょう。
学童業界を希望するなら異動や他の学童クラブへも有りです
先にも書いた通り『そのクラブがあなたに合わなかった』という事も大いにあります。
他分野、例えばスポーツでも監督の方針とは合わずに起用されなかっただけの選手も、他のチームに行った場合にとてつもなく大活躍をする場合だってあります。



『あなたにとって活躍ができる場所』、『あなたを大切にしてくれる場所』があるはずです。入ってみないと分からないという事にはなりますが、大切にしてくれない場所に長居することはありません。



学童業界での仕事がイヤになった訳ではないのなら、まだまだ学童業界で働くことは有りだとおもいます。
系列学童があるなら異動希望を出したり、一旦退職して違う学童を探すもありね!!
クラブによってカラーや雰囲気が大きく異なる事も多いです。今のクラブで、すでに出来上がってしまっている人間関係を改善していく事は難しいでしょう。という事は場所が変わればうまくいく場合も可能性としては十分にあるでしょう。
他の学童で上手く働き続けることができれば、辞めた場所はたまたま合わなかっただけという事になります。新天地で大活躍できれば逃がした魚は大きいと思わせてやることもできるはずです。
思い切って他業種へ移る
学童保育業界に辟易してしまっている人も多いはずです。そういった方は全く関連のない他分野に移ってみる、子ども関係ではあるが学童保育業界ではない分野に移ってみる事も視野に入れておくことも必要ではないでしょうか?
20代〜30代位の方でしたら学童保育業界しか経験がない、これまで学習したことが少ないといった場合の人もいるかと思います。生活に困らないくらいの金銭的に余裕があったり、時間的にも余裕があれば資格を取得の為に学習をしたり、社員登用のあるようなアルバイトなどから経験を積みつつ働くという手段もありそうです。
余裕があればですが、次のようなステップで考えるのは如何でしょうか?
学童保育で働くことで身につけたスキルや経験を整理し、自分がどのような能力を持っているかを明確にします。例えば、子どもとのコミュニケーション能力や教育プログラムの企画・運営、保護者とのコミュニケーション能力などが挙げられます。
自分が持っているスキルや経験を活かせる、興味を持っている業種を探します。例えば、教育関係の業種や人と接することが多いサービス業などが考えられます。
転職先の求人情報を収集します。インターネットの求人サイトやハローワークなどで探すことができます。また、人脈を活かして、友人や知人から情報を聞くことも有効です。
自分のスキルや経験を活かした履歴書や職務経歴書を作成します。学童保育での経験をどのように転職先で活かせるかを明確にし、アピールポイントを作りましょう。
面接では、自分が持っているスキルや経験を具体的にアピールすることが重要です。また、転職先の業種に関する情報を事前に収集し、自分がどのような役割を果たせるかをイメージしておくことが大切です。
以上のようなステップを踏むことで、学童保育から他業種への転職がスムーズに進む可能性が高まります。
辞める選択をしたら
正規の手続きで退職しましょう
就業規則や法に基づいて退職の手続きをすることが望ましいです。不要なトラブルは避け、次に向けてスムーズに進んでいくことができることが望ましいです。
退職する意思を決めたら、まずは退職届を提出する必要があります。
退職届は、書面で提出することが一般的です。退職届の提出時期や書式は、所属する学童保育施設の規定に従って確認しましょう。



「年度の切り替えまで」「契約期間まで」はなどと責任感の強い方や真面目な方は思って無理をしてしまいますが、まずは自分の事を優先しても良いと思います。
真面目な方で期間を満了するまで年度末までと考えて、身体的にも精神的にも無理をしてしまい壊してしまうことは絶対にないようにして下さい。
何度も記載しておきますが、まずは自分を優先にして下さい。身体も心も殺されてしまうということにはならないようにして下さい。
退職手続きの期間は、労働契約書や就業規則に明記されている場合があります。一般的には、2週間前までに退職の意思を雇用主に伝え、その後に手続きを進めることが望ましいとされています。
ただし、法律で定められた退職手続きの期間はありませんので、雇用主と協議して決めることになります。場合によっては、退職の理由や業務上の都合などによって退職手続きの期間が異なる場合があります。
有給休暇が残っているなら取得してしっかり休んで「次に備える、普段の生活に支障がでない」ようにして下さい。せっかくの権利なのできっちり取ってやめていってやりましょう。貯金等あり金銭的に余裕があるなら休んでしまっても良いです。
働くことができなくなってしまった事にはクラブの責任も大きいと思います。人員の補充は学童自体の仕事となります。
余裕があるなら
普段の勤務に行くだけで精一杯の人も多いでしょう。しかし、収入が無くなってしまうと生活にも支障が出てしまう人もいるでしょう。
失業保険等が支給されるのでしたら、その期間は安心かもしれませんが、働かなければならない人は無職期間が長くなることにも不安になってしまう人もいる事でしょう。
失業保険は、雇用保険に加入している方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。以下の条件を満たす場合、失業保険を受け取ることができます。
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険被保険者であること
- 最近の被保険者期間内に、被保険者である期間が1年以上あること
失業保険は、受給期間や受給額などについて、詳細な規定があります。受給期間は、被保険者期間や年齢によって異なりますが、受給することができます。また、受給額は、前年度の平均所得や被保険者期間によって決定されます。
失業保険の受給には、雇用保険の受給申請が必要です。申請方法や必要書類は、労働局などで確認することができます
動く事ができるエネルギーがあるのでしたら、働かなければならない方は、次に働く場所を求めての就職活動も並行してできると良いと思います。



勤務の無い日や時間、有給休暇を取得して面接や職場見学に行ったりしておくことも場合によってはやっておくと良いと思います。
最後に
本当は続けたかったけれど不本意ながら辞めていく決断をする方も多いと思います。今回、主に書いた、学童の仕事に合わなかった、力不足だったという事だけでなく、給与水準が低いからという事だってあります。
学童指導員として働くことは、子どもたちと一緒に過ごすことができるやりがいのある仕事ですが、一方でつらいこともあります。
以下に、学童指導員がつらいと感じることをいくつか挙げてみます。
- 子どもたちの問題行動やトラブルに対処することが多く、保護者対応も加わってくる。
- 過剰なサービスを求められてしまう。
- 給料が低いため、生活が厳しいことがある。
- 働き方が不規則で、休日出勤や残業が多いことがある。
- 上司や同僚との人間関係が悪く、ストレスを感じることがある。
- 子どもたちの成長や進路に責任を感じ、プレッシャーを感じることがある。
これらの理由から、学童指導員がつらいと感じることがあるかもしれません。
もし自分が学童指導員として働くことについて、つらさを感じるようになった場合は、自分のキャリアや生活設計などを見直すことが必要です。
また、専門的な相談機関やカウンセリングなどを受けることも考えてみると良いでしょう。
真面目で責任感の強い方は”つらい”と感じていても、決められた期間内だったり・切りの良い時期までは頑張ろうとしてさらに心身共に疲弊・病気になってしまう事もあるでしょう。
無理をして続ける前に休む・辞めるという選択をすることはとても重要です。



私も学童保育業界で働いている1人ですが、労働時間・労力の割に給与は低く、責任は重く、様々な事にも対応しなければならない、各事業所・行政のサポートは手厚くない、あげだしたら切りがないくらい整備が不十分な業種の1つとなります。



あまり良くない学童でしたら、さっさと見切りをつけても正直良いと思うわ。やりがいだけではやはり人は動けないし、辛くなるだけよ。
必ずあなたに合う場所はあるはずです。その場所を見つける為にも休む場面ならばしっかりと休んでください。心身ともに休息が必要な時は誰にでもあります。しっかりと心身を整えてから次に進んでも大丈夫でしょう。
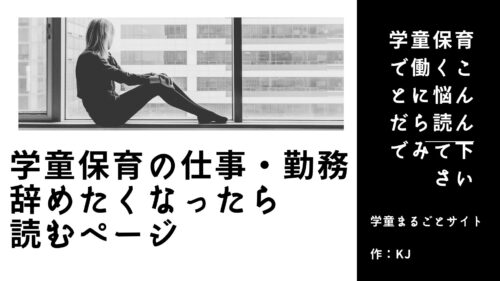
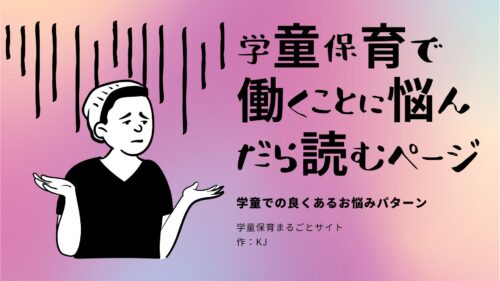
コメント